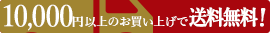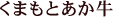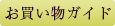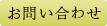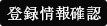2025.04.19
【お中元の添え状】書き方&文例|マナーを押さえて好印象を与えるコツ

お中元には、添え状を付けるのが一般的です。はじめて添え状を書く場合には、正しい書き方をしっかりと理解しておく必要があるでしょう。本記事では、添え状の正しい書き方から、相手別の文例をご紹介します。
さらに、お中元を渡す際の具体的な注意点についてもまとめました。お中元の添え状を初めて書く方や、失礼のないようにお中元を渡したいという方はぜひ参考にしてください。
目次
お中元の添え状とは?正しい書き方
お中元を郵送する場合には、添え状と呼ばれる挨拶状を用意しなければなりません。添え状は、お中元の品物に添えて送るお手紙のことです。そのほかに、品物が届く前に送る送り状もあります。
相手の予定などを考えて、目上の方に対しては、お中元が手元に届く前に送り状を送るのが通例とされています。しかし、直接お中元を渡す場合などは、添え状が必要になるケースもあるでしょう。まずは、お中元の添え状の基本的な構成と文例をご紹介します。
基本的な構成
お中元の添え状には、基本的な構成があります。基本構成を覚えておけば、組み合わせることでさまざまなパターンの添え状を作成できるでしょう。添え状の基本構成には、季節に合わせた挨拶や日頃の感謝、文章の結びの言葉を添えます。
なお、添え状の文章のはじめには、頭語や結語を付けるのも忘れないようにしましょう。拝啓の場合は敬具、謹啓の場合は謹言など、組み合わせて覚えておくのがおすすめです。ここからは、基本的な構成についてそれぞれ解説します。
時候の挨拶
時候の挨拶は、添え状などの挨拶状のはじめに来る季節を表す言葉を用いた文章です。なお、お中元の時期は、関東や東北は7月初旬から15日、北海道から関西、中国地方などは7月中旬から8月15日までとされています。そのため、7月・8月の時候の挨拶を使用しましょう。
7月の時候の挨拶には、「炎暑の候」「盛夏の候」や、「連日厳しい暑さが続いています」などがあります。8月の時候の挨拶では「晩夏の候」や「残暑お見舞い申し上げます」などが一般的です。
謝辞
謝辞とは、お相手への感謝の気持ちを伝える一文です。この一年の感謝を記すとともに、相手の健康を気遣う言葉を添えるなど、心が伝わるような文章を考えましょう。
さらに、これからのお付き合いに関して、これまでと変わらぬお付き合いを望むような一文を加えるのもよいでしょう。
仕事関係で取引先の方にお中元を贈る場合には、ビジネスマナーを踏まえた文章を添えるとよいでしょう。親戚や友人など親しい方の場合には、プライベートなことを交えた文章にするのもよいとされています。
結びの言葉
結びの言葉とは、添え状の最後を締めくくる言葉です。目上の方への添え状の場合には「略儀ながらお中元のご挨拶とさせていただきます」などかしこまった挨拶をしましょう。親しい方の場合は「お中元のご挨拶まで」ととどめる場合もあります。
目上の方に送る際には、文章の始めに「頭語」を、締めくくりに「結語」を忘れずに付けましょう。「拝啓」「敬具」のほか、より丁寧な添え状の場合には「謹啓」「謹言」などが使用されます。
文例
お中元のお相手には、親族などの家族や親しい友人、ビジネス関係の方、さらには上司やお世話になった方などさまざまなパターンが考えられます。お中元の添え状には、相手に敬意を表す言葉を選ぶとともに、お互いの立場をわきまえたうえで、失礼のないお手紙を書かなければなりません。
時間がある場合には、手書きでお手紙を作成するのもおすすめです。ここからは、親しい人・ビジネス関係・目上の方のそれぞれに向けた文章例をご紹介します。
家族や友人などの親しい人
拝啓
厳しい暑さが続いています。いかがお過ごしでしょうか。
平素は、お気遣いいただき誠にありがとうございます。
日頃の感謝をお伝えしたく、○○をお送りします。
お喜びいただけると幸いです。暑い日が続きますが、体調を崩されませぬようご自愛ください。
まずは書中にて、ご挨拶まで。敬具
親しい人の場合には「拝啓」「敬具」を使用するか、なにも付けないのが一般的です。時候の挨拶もカジュアルな文章がよいでしょう。最後は「ご挨拶まで」ととどめておきましょう。
ビジネス関係の知人・取引先
謹啓
盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は公私にわたりご厚情を賜り感謝申し上げます。
ご挨拶にお伺いすべきところ失礼とは存じますが、日頃のお礼までにお中元をお贈りいたします。
ご笑納いただければ幸いに存じます。暑さ厳しき折、皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
略儀ながらお中元のご挨拶とさせていただきます。謹言
ビジネス関係の場合は、尊敬語を正しく使うことが大切です。また、仕事のことについても触れるような文章にするとよいでしょう。
お世話になった人・目上の人
拝啓
盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格段のお引き立てにあずかり、御礼申し上げます。日頃の感謝を込めて、お中元の品をお送りいたします。
ご笑納いただければ幸いに存じます。お身体の具合を崩されぬよう、ご自愛ください。
略儀ながらお中元のご挨拶とさせていただきます。敬具
お世話になった方への添え状の場合には、日頃の感謝やお礼をしっかりと込めましょう。また、相手の体調を気遣うなど、お世話になっているからこその思いやりの一文を込めるのもおすすめです。
お中元の添え状を書く際の注意点

お中元の添え状を書く際には、気を付けなければならない注意点があります。添え状は、相手に心が伝わるような文章にすることが大切です。また、不吉な印象を与える言葉を避け、相手に合わせた言葉選びを心がけましょう。
お中元には、お中元を相手に贈ったことを知らせる「送り状」があります。添え状を書く前には、送り状との違いを理解しておかなければなりません。ここで、お中元の添え状を書く場合の注意点を見ていきましょう。
忌み言葉
忌み言葉とは、相手に不吉な印象を与える言葉を意味します。たとえば、切れる・壊れる・終わるなどが代表的です。これらは、結婚式などのお祝いごとでも使用しないこととされています。お中元の添え状にも使わないのが一般的です。
そのほか、相手に失礼がないように宛先や宛名の書き方についても気を付けなければなりません。相手との関係と添え状の内容がしっかりと合致していることはもちろん、失礼がないこと、さらには忌み言葉がないことをチェックしてから贈りましょう。
添え状と送り状の違い
お中元には、添え状と送り状の2つがあります。添え状は、お中元に同封するお手紙です。添え状は、封筒に入れて封をすると、お中元に同封できないという規定があります。封筒に入れる際には、封をしないようにしなければなりません。
一方で送り状とは、品物に先駆けて送ります。ハガキで送る場合もありますが、ビジネスシーンでは封書で送るのが基本的なマナーとされています。目上の方にお中元を贈る場合には、確実に受け取れるように送り状を送付すると親切です。
お中元の添え状の基本マナー
お中元の添え状は、相手への気遣いが通じるように書かなければなりません。一方的な内容にならないように気を付けましょう。前述したように忌み言葉を使わないような文章にするのはもちろん、相手に合わせた文章にすることも重要です。
また、渡すタイミングやお中元が届く時期についても配慮が必要です。ここからは、お中元の添え状に関する基本マナーについて詳しく解説します。
渡すタイミング
添え状は、自宅などに訪問して直接お中元を手渡しするときに一緒に渡します。郵送の場合は、相手にお中元を贈る際に一緒に添えるのが一般的です。
もともと、お中元は自宅に訪問して感謝の言葉を添えるのが通例でした。しかし、配送を希望する方が増えたために普及したのが添え状とされています。
なお、デパートなどでは添え状を同封して配送を手配してくれますが、添え状に対応していないお店もあります。そのため、お中元の品に添え状を同封して贈りたい場合には、事前に確認しておきましょう。
文章のポイント
添え状を書くときには、基本的な構成を守らなければなりません。頭語は、決まった組み合わせを用いるようにしましょう。また、お中元は季節ならではの風習のため、時候の挨拶が欠かせません。時候の挨拶は季節に沿うものを使う必要があるでしょう。
時候の文章のあとには、お中元の季節に合わせて体調を気遣う文章を入れましょう。このように、お中元の添え状を書くときには、一連の流れとルールを守ることが大切です。
相手に合わせた文体
添え状は、自身と相手との関係性を踏まえて適切な文体にしなければなりません。頭語・結語では、親しい関係の相手の場合、拝啓・敬具、拝呈・拝具などの組み合わせを使います。目上の方の場合、謹啓・謹言など丁寧な言葉を使いましょう。
相手の近況や健康を気遣う一文では、ビジネスや目上の方の場合、くだけた表現を避けなければなりません。親しい相手の場合には、かしこまり過ぎず「いかがお過ごしでしょうか」などくだけた文章がよいでしょう。
近況報告など
相手が親しい関係の場合には、相手の近況や健康を気遣った際に、自身の近況を盛り込むのもよいでしょう。親戚や友人であれば、自身の家族について一文織り交ぜるのもおすすめです。忙しくてなかなかお会いできない相手であれば、ご無沙汰していることをお詫びする文章も添えましょう。
ビジネスの相手や目上の相手の場合には、近況報告は省いてもかまいません。一般的に、仕事に関係する内容を書くケースが多いとされています。
お中元が届く時期
添え状の場合には、お中元と一緒に渡すため、お中元が届く時期についての文言は省きましょう。なお、送り状の場合には、お中元が届く具体的な日時を記載しなければなりません。
お中元が届く時期を明記するだけでなく、品物を選んだ理由についても書きましょう。「日頃の感謝のしるしとして」とするのはもちろん「ささやかではありますが」など、謙遜する言葉を添えると、より丁寧な印象になります。
送り状も添え状と同じように、相手に合わせた文体を選ぶことが大切です。
添え状は手書きじゃなきゃダメ?
添え状は手書きでなければならないという明確なルールはありません。近年はデジタル化が進み、手書きする方も減ってきました。とくに、ネット通販サイトなどでお中元を贈る場合には、テンプレートなどが用意されており、手書きしないケースもあるでしょう。
しかし、お中元の送り状や添え状は手書きが望ましいとされています。送り状や添え状は、相手への気持ちを伝えるために作成するものだからです。パソコンで作られたものやテンプレートのものよりも、手書きのほうが各段に相手への敬意や気持ちが伝わるでしょう。
なお、お中元を何件も贈る場合には、パソコンで添え状を作るケースもあります。パソコンで作成する場合には、名前だけでも手書きにするとよいでしょう。
お中元を渡すときのポイント

ここからは、お中元を渡すときのポイントについてご紹介します。せっかく心を込めて選んだお中元も、渡し方を一歩間違えると失礼に当たってしまうため注意が必要です。
手渡しの場合には、訪問前に必ず連絡をするとともに、外のしを付けて風呂敷や紙袋に入れるなどのルールを守らなければなりません。
発送する場合には、受け取る相手に迷惑がかからないように配送日時に配慮する必要があります。ここでは、お中元を渡すときのポイントについて、手渡しの場合と発送する場合のそれぞれについて詳しく解説します。
手渡しの場合
お中元を手渡しする際には、訪問する前に電話などで連絡をとりましょう。なお、訪問日時は日中であることが望ましいとされています。また、手渡しの際には、品物を直接持参するのではなく、必ず風呂敷や紙袋に入れておきましょう。
お中元にはのしも付けなければなりません。包装紙の上からでも用途が分かるよう、外のしを付けるのがマナーです。
ご自宅の玄関先で品物をお渡しする場合には、風呂敷を抱えて利き手でほどきます。お中元の品をかかえたまま利き手で風呂敷を折り畳み、両手で品物を渡しましょう。室内に通された場合には、挨拶を済ませてからお中元を取り出して相手に正面が向くように渡します。
外出先でお渡しする際にも、風呂敷や手提げ袋から出して渡すのが一般的です。しかし、相手が持ち歩く場合には手提げ袋ごと渡しましょう。
発送する場合
お中元を配送する場合には、手渡しにはない配慮が必要です。相手が不在のときにお中元が配送されないよう、送り状を書くのが好ましいといえます。なお、送り状は、お中元が配送される2・3日前に届くようにするとよいでしょう。
ギフトショップやデパートなどでお中元の配送手配をする場合には、前もって添え状を用意しておきます。なお、添え状を封筒に入れる場合、封をしてしまうと信書扱いになり、お中元に同封できません。お店に添え状を持って行く場合には、封をせずに持参しましょう。
配送の場合は、内のしを選ぶのが一般的とされています。内のしにすれば、配送の際にのしが破れたり汚れたりすることを避けられるからです。手渡しの場合は外のし、配送の場合は内のしとなるため、間違えないように気を付けましょう。
大切な方へのギフトに迷ったときは、馬肉を贈るのもおすすめです。
こちらの記事では、ギフトに馬肉をおすすめする理由を詳しく解説しています。
ぜひご覧ください。
お中元に添え状をつけないケース
ここまで、お中元に同封する添え状について解説しましたが、添え状を付ける必要がない場合もあります。最近では、親しい間柄の場合には、メールや電話などで感謝の気持ちを伝えるケースも増えています。
しかし、取引先の方や目上の方にお中元を贈る際には、手書きの添え状を贈るのがベストといえるでしょう。ここからは、お中元に添え状を付けない場合はどんな間柄であるかや、添え状を書かない場合に代わりとなる方法について解説します。
手紙にこだわらなくてもよい場合
贈る相手によっては、手書きの添え状にこだわる必要はありません。たとえば、家族や会社の同僚であれば、かしこまった添え状は相手が謙遜してしまうでしょう。添え状や送り状などの手紙を書かずに、お中元を贈ったことを伝えて挨拶にとどめるなどの方法もあります。
なお、親しい間柄であっても、お中元が受け取れない事態を避けるため、配達日時を伝えておくことが大切です。手紙にこだわらない場合は、相手に直接会ったときに伝えるなどの配慮を心がけましょう。
電話
お中元を贈る相手が家族や同僚で、なかなか会えない場合には、電話で挨拶するのもよいでしょう。受け取るお相手の予定を考えて、お中元が届く日時を明確に伝えておきましょう。
ビジネスや目上の方の場合には、電話で済ませるとマナー違反とされるため注意が必要です。また、親しい間でも、家族や同僚以外の場合には、添え状を用意するのが好ましいでしょう。
メール
デジタル化が進むなか、お中元の挨拶をメールで済ませる方も増えています。電話の場合と同じように家族や同僚・友人などは、メールを利用するのもよいでしょう。
メールでの挨拶では、お中元を贈ったことやお中元の配送日時について詳しく記載する必要があります。相手との関係性にもよりますが、フランクになりすぎないように、日頃の感謝が伝わるような内容にしましょう。
あえて手紙を書くなら
手紙を送る機会が減っているなか、あえて添え状を書いて相手への感謝を伝えたいという場合もあるでしょう。親しい間柄の場合には、ハガキを使用して短い文章のお礼と挨拶を記して、お中元についてお知らせするのもよいかもしれません。
家族や同僚でもお中元に手紙を同封したいときには、メッセージカードなどカジュアルなものを使用するのもおすすめです。メッセージカードにひとこと添えるだけでも、十分に気持ちが伝わるようなギフトになるでしょう。
まとめ
お中元は、日頃の感謝を大切な方に伝えるために役立つ日本ならではの風習です。相手への敬意や感謝を伝えるためには、マナーを守って正しい添え状を同封する必要があるでしょう。
添え状に使用される文章は、現代の言葉とは違う日本語の使い方やルールに基づいて書く必要があります。正しい日本語を使って、相手への敬意が伝わるような添え状を目指しましょう。
肉の大栄では、お中元にぴったりなギフトセットを多数販売しています。カタログギフトなどもあり、ご家族やご友人はもちろん、目上の方や取引先の方へのお中元にもおすすめです。感謝の思いが伝わるような特別なギフトをお探しの方は、ぜひご利用ください。

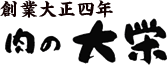
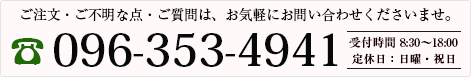
 096-353-4941
096-353-4941