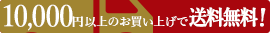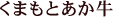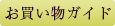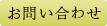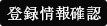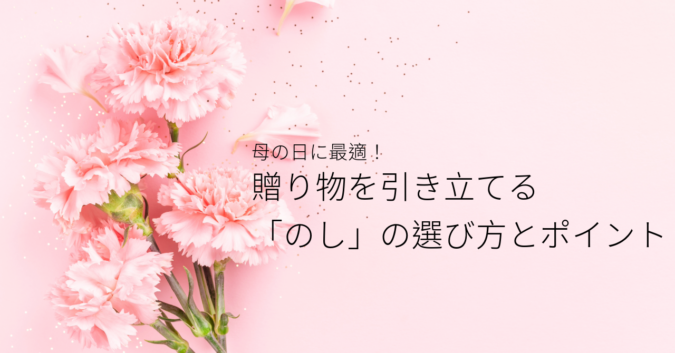2025.03.18
母の日に最適!贈り物を引き立てる「のし」の選び方とポイント
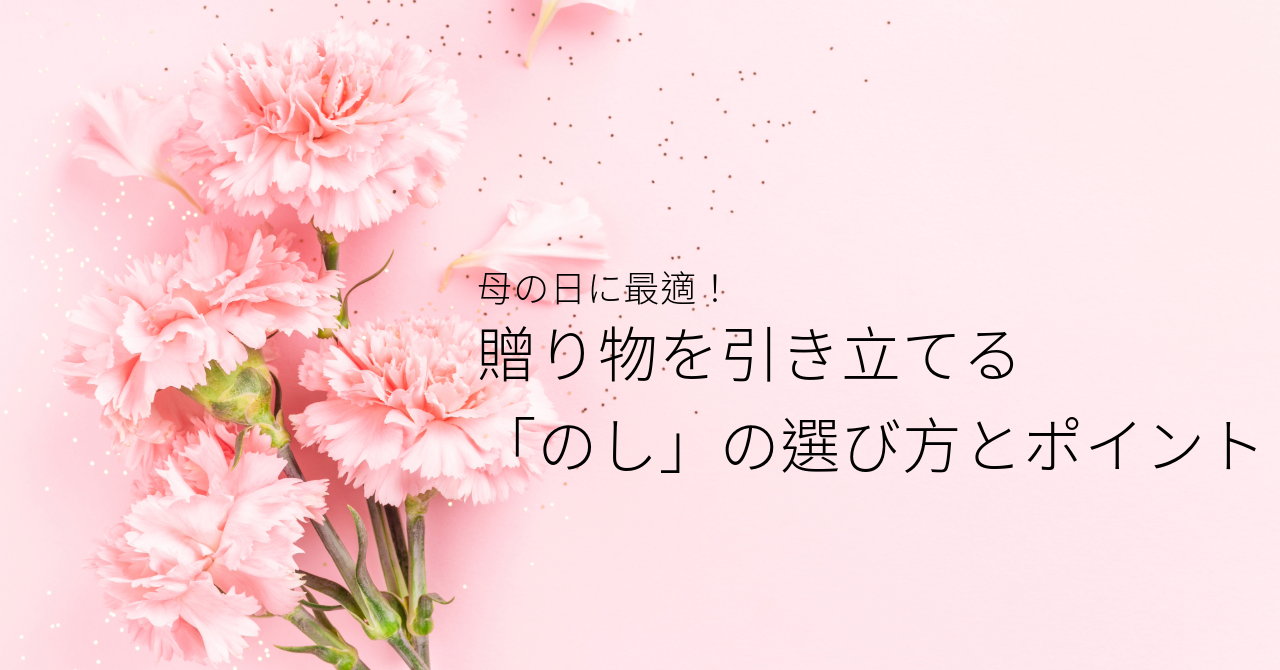
母の日の贈り物をより特別なものにするためには、プレゼントの中身だけでなく「のし」にもこだわることが大切です。「のし」は、感謝の気持ちを丁寧に伝える役割を持ち、贈り物に格式と心遣いを添える、日本独自の美しい文化です。
しかし、母の日の贈り物だからこそ「普段から仲良くしている間柄でも『のし』をつけなきゃいけないの?」といった疑問を抱く方は少なくないでしょう。また、表書きの書き方や水引の種類、外のし・内のしの使い分けなど、正しいマナーを知らないと迷ってしまうこともあります。
本記事では、母の日の贈り物に添える「のし」のマナーと、そのポイントを詳しく解説します。記事の後半では、母の日のおすすめギフトや、避けたいNGギフトも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
母の日の贈り物に「のし」は必要?
母の日は、日頃の感謝を込めて特別な贈り物をする大切な日です。しかし、贈り物を選ぶ際に「のし」をつけるべきかどうか悩む方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、外国由来の文化である母の日の贈り物には、「のし」に関する厳格なルールはありません。すなわち、つけても、つけなくてもよいのです。
とはいえ、日本人の感覚としては、ここぞというときの大切な贈り物には「のし」を添えるといった考え方が根付いているのも確かです。ここでは、母の日の贈り物で「のし」が必要だと考えられるケースについて、詳しく解説します。
「のし」が必要なケース
母の日の贈り物で「のし」が必要なのは、以下のようなケースです。
- 改まった形で感謝を伝えたい場合
- 高額な贈り物をする場合
- 義母の家に持参する場合
まず挙げられるのが、改まった形で感謝を伝えたい場合です。たとえば、初めて母の日の贈り物をする場合や、還暦など大きな節目の前後などが該当するでしょう。このようなケースでは、きちんとした形式を整えるために「のし」をつけるのが適しています。
高額な贈り物にも、「のし」をつけるのが一般的です。たとえば、ブランド品や高級ギフトセットなどの場合には「のし」をつけることで、贈り物の格式を高められます。
義理のお母さんへの贈り物など、先方の家を訪問して贈り物を手渡す場合にも「のし」をつけておくことで、贈る側の意図が明確になるといったメリットがあります。受け取る側にとっても正式な贈り物として認識しやすく、スムーズに受け取ることができるでしょう。
「のし」をつけなくても問題ないケース
一方で、以下のような場合には「のし」は不要だと考えてよいでしょう。
- カジュアルに贈る場合
- 現金や商品券を贈る場合
実母や、普段から頻繁に連絡を取り合って親しくしている義母など、形式ばったマナーを気にしないカジュアルな関係性であれば、あえて「のし」をつけずフランクな雰囲気で贈るのもよいでしょう。
その代わりに、可愛らしいメッセージカードを添えたり、素敵な包装紙を選んだり、リボンに造花の飾りを付けたりと、ラッピングにこだわることで「お母さんありがとう」の気持ちを伝えるのがおすすめです。
また、現金や商品券を選ぶ場合は「のし」は不要です。表書きには「御祝儀」などとせず、贈答用の封筒に入れるのが一般的です。
母の日の起源と「のし」の文化

母の日は、世界中で感謝の気持ちを伝える特別な日として広く親しまれています。しかし、その起源や歴史について詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
また、日本の贈答文化に欠かせない「のし」についても理解を深めておきましょう。ここでは、母の日のはじまりと「のし」の文化について解説します。
母の日の起源
母の日の起源は、1900年代初頭のアメリカに遡ります。アンナ・ジャービスという女性が、亡き母の追悼として白いカーネーションを配ったことがきっかけとされ、その想いがやがて「母親へ感謝を伝える日」として全米に広がりました。
1914年には、当時のウッドロウ・ウィルソン大統領によって、5月の第2日曜日が正式な国民の祝日として制定されました。
日本には、1910年代にキリスト教系の団体を通じて母の日の文化が伝わりました。当初は、キリスト教の影響が強かったこともあり、特定の教会や学校などで祝われる程度でしたが、昭和初期には皇后の誕生日である3月6日を母の日とする動きも見られました。
しかし、戦後になるとアメリカの習慣に倣って、5月の第2日曜日が全国的な「母の日」として定着し、現在に至ります。
日本における母の日の習慣
日本における母の日の習慣として、カーネーションを贈ることが広く知られています。赤いカーネーションは母への愛や感謝を象徴し、贈り物として人気があります。
また、近年ではカーネーション以外にも、鉢植えの花やスイーツ、実用的なプレゼントを選ぶ人も増えています。食事に関しては、母をねぎらうためにレストランでの食事や、父や子どもなどの家族が手作り料理を振る舞う習慣も根付いています。
さらに、感謝の気持ちを伝えるメッセージカードを添えることも一般的で、直筆の手紙やユニークなデザインのカードが人気を集めています。母の日専用に作られたメッセージカードなども豊富に販売されています。
「のし」の文化と母の日
本来「のし」は、「のし」紙の右上に印字された飾りのことを指しており、漢字で「熨斗」と書きます。この「のし」の文化は、日本において長年にわたり贈答の場面で重要な役割を果たしてきました。
もともと「のし」は、贈り物に添える飾りとしての意味を持ち、古くは乾燥させた鮑(あわび)を細く伸ばして添えることが由来とされています。これは、鮑が長寿や繁栄を象徴する縁起物とされていたためで、贈り物をより格式高くし、受け取る側への敬意を示すものとして用いられてきました。
また、のし紙は、神前に供える奉納品を和紙で包み、紙縒りで束ねたことがはじまりです。現在では「のし」を印刷した「のし紙」として簡略化され、さまざまなシーンで活用されています。
たとえば、慶事や弔事、企業間の贈答、個人間のプレゼントなど、幅広い場面で使用されるようになり、贈る側の心遣いや礼儀を表す重要な要素となっています。
「のし」は単なる装飾ではなく、日本独自の文化として根付いており、贈り物に込めた気持ちをより深く伝える役割を担っています。母の日の贈り物に「のし」を添えることで、感謝の気持ちをより丁寧に伝え、特別な1日をさらに印象深いものにできるでしょう。
母の日の贈り物にかける「のし」のマナー

ここでは、母の日の贈り物に「のし」をつける際の表書きや名前の書き方、水引の種類、外のし・内のしの使い分けについて解説します。感謝の気持ちをしっかりと伝えるために、母の日に適した「のし」のマナーを押さえておきましょう。
表書き
表書きとは、贈り物の目的を明確に伝えるために、のし紙の上部に記載する言葉のことです。贈答の場面や用途によって適切な表記が異なります。毛筆や筆ペンを用いて書くのが正式とされますが、最近では印刷されたものを使用するケースも増えています。
母の日の贈り物にかける「のし」の表書きは、贈る相手がお母さんであることから「感謝」や「御祝」などの一般的な表書きを省略し「母の日」とシンプルに記載するのが一般的です。これは、母の日が祝儀というよりも、日頃の感謝を伝える日であるためです。
水引
水引は、紅白の5本蝶結びを使用します。蝶結びは「何度繰り返してもよいお祝いごと」に用いられるため、毎年訪れる母の日には最適なものです。
逆に、一度きりであるべきお祝い(結婚祝いや弔事)では、結び切りの水引を使います。「おめでたいシーンや喜ばしいことに使うものだから」と混同してしまわないよう、注意しましょう。
名前
のし紙には、表書きの下に贈り主の名前を記載するのが一般的です。贈る相手に対して、誰からの贈り物なのかを明確にし、丁寧な印象を与える目的があります。贈り主の名前は、水引の下にフルネームで書くのが基本です。
「外のし」と「内のし」の使い分け
母の日の贈り物に「のし」をかける際は、贈る方法に応じて「外のし」と「内のし」を使い分けるとよいでしょう。
「外のし」は、贈り物を包装紙で包んだ上から「のし」をかける方法です。贈り物の内容が一目でわかるため、持参する場合に適しています。とくに、お母さんと離れて暮らしており、帰省の際に直接手渡す場合などにおすすめです。
「内のし」は、贈り物に直接「のし」をかけ、その上から包装紙で包む方法です。控えめで上品な印象を与えるため、宅配便などで郵送する際に適しています。「のし」が外から見えないため、受け取った側が包装を開けたときに、改めて丁寧な贈り物であることを実感できるのが特徴です。
生ものや特殊な贈り物の場合
食品やフルーツ、花などの生ものを贈る場合は「のし」を付けないのが一般的です。
生ものに直接「のし」をかけることは衛生的に適さないうえに、包装の形状によっては「のし」をかけるのが難しい場合もあるためです。その場合は、送り状やメッセージカードに「母の日の贈り物」と記載し、感謝の気持ちを伝えるのがよいでしょう。
また、カジュアルな母の日ギフトでは、「のし」を使わず、リボンやオリジナルラッピングで特別感を演出するケースもあります。お母さんの好みに合わせ、贈り方を工夫すると、より心のこもったプレゼントになるでしょう。
母の日の贈り物に適した「のし」の書き方
ここでは、母の日にぴったりな「のし」の書き方を解説します。縦書き・横書きそれぞれのパターンでの書き方も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
表書きの書き方
母の日の贈り物にかける「のし」の表書きは、縦書きと横書きで記載の位置が異なります。縦書きの場合は「のし」の中央に「母の日」と記入します。
一方、横書きの場合は、中央よりやや右側に「母の日」と記載するのが基本です。これは、表書きを目立たせつつ、バランスの取れた配置にするための配慮です。
また、母の日の贈り物にふさわしい表書きは「母の日」だけでなく「お母さんありがとう」「大好きなママへ」や「感謝」など、より温かみのあるメッセージを添えることも可能です。
ただし、格式のある贈り物として「のし」を使う場合は「母の日」とシンプルに記載するのが一般的です。手書きする場合は、楷書で丁寧に書くと、より心が伝わります。
名入れの書き方
実母であれば、苗字を省略して下の名前だけで構いません。一方で、義母に贈る場合は、苗字を一緒に書くケースも少なくないでしょう。
夫婦や兄弟姉妹で贈る場合は、それぞれの名前を並べる形式が一般的です。このとき、苗字は省き、下の名前のみを連名するとよいでしょう。
縦書きの場合は、表書きの下、中央よりやや右側に氏名を記入します。家族で贈る場合は、右詰めで子どもたちの名前を連名で書くことが多いです。一方、横書きの場合は、表書きの下、中央に氏名を記入し、家族で贈る際はその下に子どもたちの名前を並べて書きます。
そのほかにも可愛らしいひと工夫として、小さな子どもからのプレゼントとして「のし」をつける場合は、ひらがなで「〇〇より」と子どもの名前を書くのもよいでしょう。子どもらしい手書きの名前を添えることで、温かみがあり、より心のこもった贈り物になります。
表書きと名入れの位置
表書きは「のし」の中央、または中央よりもやや右側に書きます。これは、贈る目的を明確にするだけでなく「のし」紙全体のバランスを整えるためです。
名入れは、表書きの下に記載するのが基本です。個人名で贈る場合は中央に、家族連名で贈る場合は右詰めにすることで、読みやすい配置になります。
このように「のし」の書き方には一定のルールがあります。これらをきちんと丁寧に記載することで、母の日の贈り物をより丁寧で特別なものに引き立てられるでしょう。
母の日に避けたい贈り物と注意すべきポイント

母の日の贈り物を選ぶ際には、相手の好みやライフスタイルを考慮し、気持ちが伝わるものを選ぶことが重要です。とくに、避けるべき贈り物として挙げられる品物を選んでしまうと、誤解を招いたり、不快な思いをさせてしまう可能性もあるでしょう。
ここでは、贈り物としては不適切なNG例を紹介します。
菊の花・白いカーネーション
母の日に花を贈る際には、選ぶ種類に注意が必要です。菊の花は、日本ではお葬式や仏花としてのイメージが強いため、母の日の贈り物には適していません。
同様に、白いカーネーションも避けたほうがよいでしょう。白いカーネーションは、先述した母の日の発端ともなった花ですが、その背景には「亡き母を偲ぶ」といった想いがあります。供花の意味合いを持つため、母の日に贈ると誤解を招く可能性があります。
代わりに、赤やピンクのカーネーション、またはバラやユリなど、お母さんが好きな花を選ぶとよいでしょう。
ハンカチ
ハンカチは、日常的に使う実用的なアイテムではありますが、贈り物としては注意が必要です。日本では、ハンカチを贈ることが「別れ」を連想させるとされ、とくに目上の人に対するプレゼントには適さないと考えられています。
母の日の贈り物として選ぶ場合は、ハンカチ単体ではなく、スカーフやタオル、バッグなどとセットにすることで、より前向きな印象のギフトになります。
包丁・ナイフ
包丁やナイフなどの刃物類は「縁を切る」ことを連想させるため、母の日の贈り物としては避けましょう。とくに、高齢のお母さんに贈る場合には、誤解を招かないよう注意が必要です。
ただし、料理好きのお母さんが自ら希望する場合は例外です。この場合は、有名な調理器具メーカーの包丁やブランドのナイフなど、お母さんが本当に喜ぶアイテムを選べば贈っても構いません。
また、メッセージカードを添えて、感謝の気持ちをしっかり伝えながらプレゼントするとよいでしょう。
櫛(くし)
櫛は「苦(く)」や「死(し)」を連想させるため、日本では古くから縁起が悪いとされています。そのため、母の日の贈り物にはふさわしくないという考え方が一般的です。
先述した包丁やナイフなどの刃物と同様、とくに年配の方の間では、このような言葉の縁起を気にすることが多いでしょう。そのため、櫛を贈る場合はとくに慎重に検討する必要があります。
どうしても美容関連のギフトを贈りたい場合は、ヘアブラシやドライヤーなど、高品質なヘアケア用品などを選ぶのがよいでしょう。
現金・金券
母の日のプレゼントとして、現金や金券を贈るのは、やや味気ない印象を与える可能性があります。感謝の気持ちを込めるという母の日の趣旨から考えると、手間をかけて選んだ贈り物のほうが、気持ちが伝わりやすくなります。
ただし、お母さん自身が好きなものを選びたい場合は、商品券やギフトカードを贈るのも一つの方法です。その際は、メッセージカードを添えて感謝の気持ちを伝えると、より心のこもった贈り物になります。
母の日の贈り物にピッタリなおすすめギフト

母の日の贈り物は、お母さんの好みやライフスタイルに合わせて選ぶことで、より喜ばれるものになります。定番のカーネーションやスイーツはもちろん、美容アイテムや健康グッズ、特別感のあるグルメギフトなど、選択肢は豊富です。
さらに、毎年同じようなプレゼントになりがちな母の日だからこそ、少し工夫を凝らしたギフトを選ぶことで、感謝の気持ちをより印象的に伝えられます。今年の母の日には、お母さんの笑顔を引き出せるような、心のこもった贈り物を選んでみましょう。
相手の趣味や好みに合わせて選ぶ
母の日の贈り物は、相手の趣味や好みに合わせることで、より喜ばれるものになります。ここでは、普段の生活スタイルや好きなものから連想できるギフト例をピックアップしました。
お花
花束は、母の日の定番ギフトのひとつです。美しい花々は、視覚的にも癒しを与え、部屋を華やかに彩ってくれます。カーネーションをはじめ、バラやガーベラ、胡蝶蘭なども人気です。最近では、長く楽しめるプリザーブドフラワーやハーバリウムを選ぶ人も増えています。
また、鉢植えの花も母の日の贈り物として人気があります。とくに、ガーデニングが好きなお母さんには、自宅の庭やベランダで育てられる鉢植えの花が喜ばれるでしょう。カーネーションやアジサイ、ミニバラなど、成長を楽しめる花を選ぶことで、母の日の思い出を長く楽しんでもらうことができます。
鉢植えは、水やりやお手入れをすることで長く育てられるため、愛情を込めて世話をする楽しみも贈れるギフトといえます。
グルメギフト
食べることが好きなお母さんには、美味しいグルメギフトが最適です。高級チョコレートや和菓子、フルーツギフトなど、スイーツ系のプレゼントは喜ばれることが多いです。
また、料理好きのお母さんには、高級食材やこだわりの調味料セットなどもおすすめです。普段はなかなか買わないような特別な逸品を贈ることで、特別な日をより印象的なものにできます。贈ったグルメギフトで、お母さんと一緒に料理をするのもよいでしょう。
コスメセット
美容に関心の高いお母さんには、スキンケアやコスメセットも人気です。高品質な化粧水や美容液、エイジングケアに特化したスキンケアアイテムなどを選ぶと喜ばれます。リップクリームやハンドクリームなど、日常的に使いやすいアイテムを選ぶのも素敵でしょう。
また、リラックスタイムに使えるアロマキャンドルやバスソルトなども、美容とリラクゼーションを兼ねた贈り物として人気があります。
健康グッズ
健康を気にするお母さんには、健康に役立つアイテムを選ぶのもよいでしょう。肩や腰をケアできるマッサージ器、血圧計、快適な睡眠をサポートする枕やアイマスクなどもおすすめです。
運動が好きなお母さんには、ウォーキングシューズやフィットネス用品なども喜ばれます。日頃の健康維持に役立つアイテムをプレゼントすることで「健康に長生きしてほしい」「いつまでも元気でいてほしい」という気持ちも伝えられるでしょう。
年齢や予算に合わせた贈り物を選ぶ
母の日のプレゼントは、年齢やライフスタイルによっても最適なものが変わります。お母さんの年齢や生活スタイルを考慮し、長く愛用できるアイテムを選びましょう。
40代・50代のお母さんへおすすめのプレゼント
美容家電は、美容に関心のあるお母さんにぴったりです。美顔器やスチーマー、ヘアアイロンなど、自宅で手軽にケアできるアイテムが人気を集めています。
また、旅行好きなお母さんには、旅行券を贈るのもよいアイデアです。宿泊施設のギフト券や、食事付きの温泉旅行プランなど、特別な体験をプレゼントすることで、思い出に残る母の日になります。
60代・70代のお母さんへおすすめのプレゼント
年齢を重ねると、健康を気遣うことが増えるため、健康食品やサプリメントなどのギフトが人気です。栄養価の高いドリンクや、関節や骨の健康をサポートするサプリメントなども選ばれています。
また、リラックスできる時間を提供するアイテムとして、座り心地のよいクッションや、膝の負担を軽減するフットマッサージャー、手の疲れを癒すハンドマッサージャーなども喜ばれます。
母の日には贅沢感のあるお肉ギフトもおすすめ

母の日の贈り物として、贅沢感のあるお肉ギフトは特別な選択肢のひとつです。ここでは、母の日にお肉のギフトがおすすめな理由を紹介します。
高級感・特別感がある
母の日の贈り物として、高級なお肉ギフトは特別な贅沢を味わえる選択肢のひとつです。普段なかなか食べる機会のない和牛やブランド牛は、食卓を豪華に演出し、特別な日にふさわしい贈り物となります。
とくに、霜降りの美しい黒毛和牛や、旨みの詰まった熟成肉は、高級感とともに上質な味わいを楽しめるため、母の日にぴったりです。
家族と一緒に楽しむことができる
お肉ギフトは、ひとりで楽しむだけでなく、家族と一緒に食卓を囲む機会を提供する点も魅力です。母の日に家族が集まり、おいしいお肉を囲んで食事を楽しむことで、感謝の気持ちを直接伝える時間を持つことができます。
ステーキや焼肉、すき焼きなど、調理方法を選べるのもうれしいポイントです。
珍しいので差別化できる
母の日の贈り物は花やスイーツが定番ですが、お肉ギフトは比較的珍しく、ほかの方からのプレゼントと差別化しやすい点も魅力です。
とくに、普段あまり食べる機会のない希少部位や、地域特産のブランド肉を選ぶことで、より特別感のあるギフトになります。たとえば、松阪牛や神戸牛、米沢牛、くまもとあか牛といった有名ブランド牛を贈ると、贅沢なひとときを演出できるでしょう。
予算や好みに合わせて柔軟に選べる
お肉ギフトは、種類や価格帯が幅広いため、予算や相手の好みに応じて選びやすい点も大きなポイントです。牛肉のほかにも、豚肉や鶏肉、馬肉、ラム肉など選択肢が豊富なため、料理のバリエーションも広がります。
ステーキや焼肉用の厚切り肉だけでなく、しゃぶしゃぶ用の薄切り肉や、味付きの加工品など、用途に応じた選び方ができる点も魅力です。
贈り物としての選び方
母の日のギフトとしてお肉を選ぶときは、以下の3つのポイントに注目しましょう。
- 品質
- 量
- 好みの食べ方
まずチェックしたいのが品質です。産地やブランドにこだわることで、より特別感を演出できます。黒毛和牛や銘柄豚、地鶏など、品質が保証されたお肉を選ぶと、贈り物としての価値が高まります。
また、適切な量を選ぶことも重要です。お母さんだけがいただくなら食べきりサイズのセット、家族みんなで団らんを楽しむならボリュームのあるギフトを選ぶとよいでしょう。
お肉の種類によって適切な調理方法も変わるため、お母さんの好みに合わせた選び方をすると喜ばれます。ステーキや焼肉用の厚切り肉、すき焼きやしゃぶしゃぶ用のスライス肉など、用途に応じたギフトセットを選ぶことで、より楽しんでもらえるでしょう。
肉の大栄では、ご贈答用に各種ギフトセットや包装をご用意しております。肉の大栄自慢のお肉を、ぜひ一度ご賞味ください。
まとめ
母の日は、日頃の感謝を込めて贈り物を贈る特別な日です。母の日は海外からの文化のため、必ずしも「のし」をつけなければならないといった決まりはありません。そのため、贈り物に「のし」をつけるかどうかは、贈り物の種類や、普段の関係性によって判断しましょう。
母の日の贈り物といえば、花やスイーツが定番ですが、特別感のあるプレゼントとして高級肉のギフトもおすすめです。普段なかなか食べる機会のない高級なお肉は、贅沢な味わいを楽しめるだけでなく、家族みんなで囲む食卓をより特別なものにしてくれるでしょう。
肉の大栄では、贈り物にぴったりな高級肉のギフトセットをご用意しています。特選の馬刺しや九州黒毛和牛、くまもとあか牛など、お肉好きの方なら思わず顔がほころぶ極上のお肉をお楽しみいただけます。もちろん、鹿児島県産黒豚や熊本県産銘柄鳥など、豚肉や鶏肉もお取り扱いがございます。
カタログギフトもご用意しておりますので、お母さんと一緒にカタログを見ながら選ぶといった楽しみ方もご提案できます。ステーキやすき焼き、しゃぶしゃぶなど、調理方法も豊富で、好みに合わせたギフト選びが可能です。
今年の母の日は、感謝の気持ちを込めて、贅沢なお肉ギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

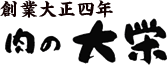
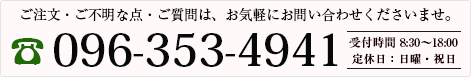
 096-353-4941
096-353-4941