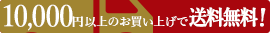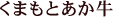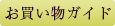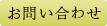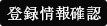2025.09.23
お中元で商品券は贈ってはいけない?マナーやNG商品を解説

お中元を贈る時期になったとき、どのようなものを贈るべきなのか、商品券を贈ってもよいのかなど悩む方も多いのではないでしょうか。とくに、初めてお中元選びをする方や仕事先でお世話になっている方へ贈る場合など、失礼のないように送りたいものです。
今回は、お中元での商品券の贈り方や贈らない方がよいもの、マナーなどについて紹介します。
目次
お中元はいつ贈る?
お中元は、いつの時期に贈るのが最適なのでしょうか。まずは、お中元を贈るタイミングについて紹介します。
全国的には7月上旬から7月15日ごろ
お中元を贈る時期は決められており、全国的には7月の上旬から7月15日ごろまでです。お中元の起源は、中国の道教に由来しており、旧暦7月15日は犯した罪を許してくれる神様の誕生日でした。
その中元が、日本の風習であるお盆に先祖様へお供えものをする習慣と重なって、お盆にお世話になった人へ贈り物をする風習が生まれ、お中元となりました。しかし、近年では、お中元の早期割引やセールなどの影響もあり、6月下旬に準備をしてそのまま発送する人も増えてきています。
早期に準備することで、余裕を持って準備できるだけでなく、相手にもスムーズに届けられるという利点があります。
また、早めに贈る場合は事前に送り状を出しておくことが親切です。送り状を送ることで、贈り物を受け取る相手にも心の準備ができ、感謝の気持ちがより丁寧に伝わります。
地域によって差がある
お中元は、贈る相手が住んでいる地域によっても時期が少し異なります。贈る相手が東日本にいる場合には7月上旬から7月15日まで、西日本にいる場合にはお盆の時期が8月のため、7月中旬から8月15日ごろまでが一般的です。
また、お中元を贈る時期ごとに表書きも変えることが大切で、8月8日までに贈る場合には暑中お見舞いとなり、8月8日以降に贈る場合には残暑お見舞いと明記します。書き方としても、上司や目上の方へ贈る場合には、暑中お伺い、残暑お伺いとする方がよいでしょう。
お中元として商品券を贈るのはやめたほうがよい?

お中元に商品券を贈ることは避けることが一般的です。お中元を贈る相手には、いつもの感謝の気持ちを示すことが目的となるため、商品券を贈ることでお金に困っているというイメージを持たせてしまうおそれがあります。
とくに、目上の方や先輩へ贈るときには避けた方がよいでしょう。しかし、両親や友人などの親しい間柄の相手であれば商品券を選んでも問題ありません。
商品券単体ではなく、お菓子やグルメなどほかのものと一緒に贈ることがおすすめです。また一言メッセージを添えることでより丁寧な印象を与えられます。
お中元として商品券を贈るメリット2つ
お中元を贈る際、相手の好みやライフスタイルに合わせて選ぶことが大切ですが、商品券を贈ることにもメリットがあります。具体的にどんなメリットがあるのか、2つのポイントをご紹介します。
相手の好みを考慮せずに贈れる
お中元として商品券を贈ることのメリットのひとつめは、相手の好みを考慮せずに贈れることです。相手の好みやライフスタイルをあまり知らない場合にも商品券であれば、気軽に間違いなくギフトとして贈れます。
また、商品券を受け取った側も、価格が一目でわかるため、お返しをするときにも金額の目安がわかりやすいです。そのため、相手の好みがあまりわからない方や目上の人ではない限りは商品券を贈ることもひとつの方法でしょう。
相手が好きなものを選べる
お中元として商品券を贈ることのメリットの2つめは、商品券を受け取った側が好きなものを選べることです。より実用性が高く、必要なものを購入できます。
相手に贈り物をするときには、家族構成なども考慮して選ぶ必要があります。商品券であれば、細かい情報も不要で、相手が好きなものを確実に送れるため喜ばれる可能性も高まります。
また、商品券は軽くてかさばらないため場所をとらず、家の間取りに関係なく受け取りやすいです。郵送でも簡単のため、遠いところに住んでいる方へのお中元でも配送しやすいでしょう。
お中元として商品券を贈る際に注意すること
お中元として商品券を贈ることは便利で実用的ですが、贈る際にはいくつかのポイントに注意が必要です。
相手に失礼がないように、適切な方法で贈るために気をつけるべきことを確認しておきましょう。ここでは、商品券を贈る際に押さえておきたい注意点を紹介します。
内祝いには選ばない
お中元として商品券を贈るときの注意点のひとつめは、基本的に内祝いには選ばないことです。結婚祝いや出産祝いなどをもらったときの内祝いとして、商品券を贈るのはマナー違反となっています。
商品券は金額が明確なため、お祝いをもらったときのお返しとして贈るのは不適切です。相手からもらった品の金額が未定の場合にはなおさら、商品券でお返しをするのはおすすめできません。
しかし、親戚や親しい友人から商品券がほしいと希望があった場合や、過去に内祝いを商品券でもらった相手には商品券を贈っても問題ないです。
商品券に対するお礼では贈らない
お中元として商品券を贈るときの注意点の2つめは、いただいた商品券に対するお礼として商品券を贈らないことです。
相手から商品券をもらった場合には、違う種類の商品券であっても、お返しに選ぶのはマナー違反です。基本的には、商品券をもらった相手には、商品券以外のグルメやお菓子などを贈るようにしましょう。
ただし、内祝いのときと同じように相手から商品券がよいというリクエストがあった場合には、商品券を贈っても問題ありません。商品券をもらった相手へは、相手から商品券がよいという要望がないときには商品券以外のものを贈るようにしましょう。
お台と一緒に贈る
お中元として商品券を贈るときの注意点の3つめは、お台と一緒に贈ることがおすすめです。お台とは、商品券や金封などを直接渡すのではなく、菓子折りを台に見立てるような形を示しています。
一部の地域では、商品券や金封をのせて贈るときの菓子折りを、お台としているところもあります。そのため、商品券を贈るときには、お菓子やハンドクリーム、お肉、ドリンクなどのプチギフトと一緒に贈るとよいでしょう。
この場合に添えるプチギフトの料金相場としては、1,000円から2,000円ほどが目安となっています。高価すぎず、安価すぎないものをプチギフトとして選び、商品券をプラスとして贈るようなイメージでもよいでしょう。
商品券をどうしてもお中元に贈りたい場合には、ほかのものと一緒に贈るようにしましょう。
お中元を贈る際のマナー

お中元を贈るときには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。ここでは、お中元を贈るときのマナーについてお伝えします。
水引と熨斗
お中元を含む、贈答品に使用する包み紙の飾り紐を水引といいますが、種類もいくつかあり、お中元には紅白の蝶結びの水引がデザインされた熨斗紙を一般的には使用します。
熨斗紙には、贈り物の箱に直接、熨斗紙を巻いて包装紙で包む内熨斗と包装紙で贈り物を包んだ上から熨斗紙を巻く外熨斗があります。お中元を手渡しするときには、外熨斗、宅配便の場合には熨斗紙が剥がれる心配のない内熨斗にすることがおすすめです。
また、熨斗紙には表書きをする必要があり、上部には「御中元」などと記載し、下の部分には送り主の名前を記載することが一般的です。名前はフルネームで書くこととされていますが、お中元の場合には名字だけでも可能です。
また、文字を記載するときには筆ペンや毛筆を使用することが正式なマナーとされていますが、近年ではマジックペンでの記載も可能です。喪中で贈る場合には、派手な水引や熨斗は付けず、無地の白い紙に表書きを記載するとよいでしょう。
料金相場
お中元は、感謝の気持ちを伝えることが趣旨となるため、高価すぎると相手に返って気を遣わせてしまうおそれがあります。また、お中元は1年で終わるものではなく、毎年継続して贈るものです。
前年よりも明らかに贈り物の金額に差があることや、昨年よりも安価な品物を贈ることはマナー違反になります。そのため、毎年贈ることを考慮し、継続可能な金額設定でお中元を贈るとよいでしょう。
贈る相手との関係性によっても金額設定が異なり、親や親戚のような身内へ贈るときにはおおよそ3,000円から5,000円ほどであり、とくにお世話になった方や仕事関係の方へのお中元はおおよそ3,000円から10,000円ほどが相場となっています。友人や知人であれば3,000円ほどが目安です。
お中元として贈ってはいけないもの

お中元の品物を選ぶとき、相手が喜ぶものであれば可能とされていますが、実は縁起が悪いものや贈る品物としておすすめできないものがあります。ここでは、お中元として贈ってはいけないものをいくつか紹介します。
ハンカチ
ハンカチは、誕生日などのプレゼントとしても重宝されているギフトのひとつですが、実は縁起が悪いという考えもあります。ハンカチは、日本語で手切れということからも縁が切れてしまうことや、ハンカチで涙を拭いたりする点からも別れを連想させてしまう可能性があります。
タオルギフトを贈りたい場合には、ハンカチではなく今治バスタオルなどがよいでしょう。
お花
お花もギフトとして贈られることが多いもののひとつですが、花自体に問題がある訳ではなく、花言葉やその花が使われているシーンに気をつけて選ぶことが大切です。
たとえば、彼岸花はその美しい姿とは裏腹に、花言葉に「悲しい思い出」や「あきらめ」を意味するものがあり、毒を含んでいることから、食べると命に関わる危険性があるため「死」を連想させてしまうことがあります。
また、菊は花言葉に問題はなくとも、葬儀で使われることが多いお花であるため不向きです。ほかにも、椿やサルスベリ、フジ、ビワなどがあげられます。
お花を贈る際には、その花が持つ意味や使用される状況について十分に理解し、慎重に選ぶことが重要です。贈る相手や場面に合った花を選ぶことで、より気持ちを伝えられます。
刃物
刃物は縁が切れることを連想させてしまうため、お中元に限らず、贈り物として避けられることが一般的です。
とくに、お中元やお祝いのギフトとして贈る場合、今後も良好な関係を続けたい相手に対しては刃物を贈ることが無礼に思われてしまうことがあります。このような象徴的な意味を避けるためにも、刃物は贈り物として不向きとされています。
文房具
文房具には「もっと真面目に働く」や「もっと勤勉に」という意味合いが込められているとされるため、目上の方や先輩に対して贈ると、相手に対して改善を求めているかのような印象を与えてしまうことがあります。このため、贈り物としては不適切とされています。
一方で、文房具は同期や後輩への贈り物としては問題ありません。
履き物
履き物でも、目上の方や先輩への贈り物には不適切です。靴下や靴などには、足で踏みつけるという意味合いがあることや、肌着、下着類には「着るものに困っているから恵んであげる」といった意味を連想させてしまう可能性があります。
お中元だけではなく、ギフトには不向きといえます。とくに、目上の方や先輩へのお中元としては選ばないほうがよいでしょう。
相手に合わない食品
お中元を贈るときには、相手の家族構成や好みにも気を配りましょう。たとえば、一人暮らしの方へのお中元で5人前以上の食べ物を贈ると、場合によっては保管しきれずに困ってしまう可能性があります。
また、贈る品物は相手の好みや食生活にも注意を払うことが大切です。相手が喜んで受け取れるものを選ぶことが、贈り物の本来の目的である感謝の気持ちをしっかりと伝えることにつながります。
アルコール飲料
アルコール飲料をお中元として贈る際には、贈る相手の好みをより考慮する必要があります。アルコールは好きな人もいれば、苦手な人もいるため、相手がアルコールを好まない場合、贈り物としては喜ばれないことが多いです。
そのため、アルコールを贈る場合には、相手がアルコールを受け取ることに問題がないかを事前に確認することが望ましいです。
4・9個入りの詰め合わせギフト
お中元として詰め合わせギフトを選ぶ場合は、個数にも注意が必要です。4個入りや9個入りは「4は死」「9は苦」と読んだときに同じ音になるため、縁起の良くない数字とされています。とくに、お祝い事や感謝の気持ちを伝える贈り物としては、このような数字を避けることが一般的なマナーとなっています。
一方で、無限や末広がりの意味を持つ8は縁起の良い数字とされています。そのため、8個入りのギフトは縁起が良いとされ、とくにお祝い事や感謝の気持ちを伝える際に最適な選択肢となるでしょう。
このように、数字の意味を理解し、相手やシーンにふさわしい個数を選ぶことで、より気配りが感じられる贈り物になります。
こちらの記事では、ギフトにおすすめの馬刺しについて解説しています。3つの理由や選び方も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
今回は、お中元で商品券を贈るときのマナーや一般常識を中心に、贈り物としてふさわしくないものやおすすめ品などを紹介しました。一般的なマナーだけでなく相手によっても喜ばれる品は異なるため、状況に応じて贈り物を変えていくことが大切です。
なにを送るか迷った際には、国産の厳選されたお肉を検討してみてはいかがでしょうか?肉の大栄では、長年の経験で培われた「職人の目」で厳選した、馬刺しや黒毛和牛、あか牛などさまざまなギフトセットを用意しており、好みに合わせた内容をお選びいただけます。
お中元はもちろんのこと、各イベントに合わせた包装や熨斗を無料で提供しております。ご相談やご質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

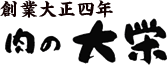
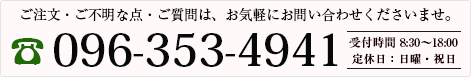
 096-353-4941
096-353-4941